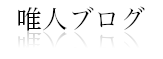日本でも長寿村と呼ばれる所が以前には確かにあった。それは、山梨県棡原村(上野原市)である。そこを研究した東北大学名誉教授の近藤正二博士によると、その土地で取れた未加工の食品を食べていたからだと報告されている。その後、そこに住んでその研究を進めている古守豊甫博士の報告によると、棡原村では、以前は次のような物を食べていたということである。そこでは、米は取れないので、昔から粟、ひえ、きび、とうもろこし、そば、麦、大豆などの雑穀に、芋類(じゃがいも、さといも、さつまいも)、こんにゃく、かぼちゃ、そのほか野菜、山菜は、季節に応じて豊富に採っていたそうである。
日本でも長寿村と呼ばれる所が以前には確かにあった。それは、山梨県棡原村(上野原市)である。そこを研究した東北大学名誉教授の近藤正二博士によると、その土地で取れた未加工の食品を食べていたからだと報告されている。その後、そこに住んでその研究を進めている古守豊甫博士の報告によると、棡原村では、以前は次のような物を食べていたということである。そこでは、米は取れないので、昔から粟、ひえ、きび、とうもろこし、そば、麦、大豆などの雑穀に、芋類(じゃがいも、さといも、さつまいも)、こんにゃく、かぼちゃ、そのほか野菜、山菜は、季節に応じて豊富に採っていたそうである。粟、ひえ、きび、とうもろこしは餅について食べ、大麦は押麦にしたり、引き割りにし、腹もちがよいので重労働の時に食べたというのである。小麦は粉にして、ほうとう(これは、山梨の郷土食で、うどんを野菜と一緒に、いきなりみそ汁の中に入れて煮込んだもの)と、まんじゅうにして食べていたということである。
そして、動物性蛋白質の肉や魚は、ほとんど口にすることはなかったというのである。
ところが、この山村にも道路が整備され、自動車が通るようになると、肉や魚や白米などが持ち込まれるようになった。そうすると、若い人々の中では、肉食、白米食をする人が増えていった。その結果、どういうことが起ったかと言うと、そういう人々に高血圧の肥満者が目立って増え、脳溢血で倒れる人がどんどん出てきた。そして今日では、その脳溢血で倒れた人たちの面倒を、その両親達が見ている有様だというのである。
日本における有数の穀倉地帯には短命が多いと近藤正二博士は「日本の長寿村・短命村」の中で書いている。具体的には、秋田県、山形県が短命県なのである。米が豊富なだけに十分精白し、たらふく食べ、畑が少ないため、野菜類は必要量を満たしていないのである。米どころでありながら長寿村である鳥取県の大山町や、徳島県の藍園村、学島村などは、売り物である米は食べず、自分たちはさつまいも、麦などを食べ、田のあぜ道に大豆やニラなどを植え、畑で野菜を作るなどして、白米を食べずに、それらのものを十分食べている。
島根県の隠岐の島は沖縄と並び、健康長寿者の多い所だが、彼らは大豆製品を毎日食べている。豆腐、納豆、あるいは、つぶし豆を乾燥させた打ち豆などである。このように食べ物が人の健康に与える影響は極めて大きい。